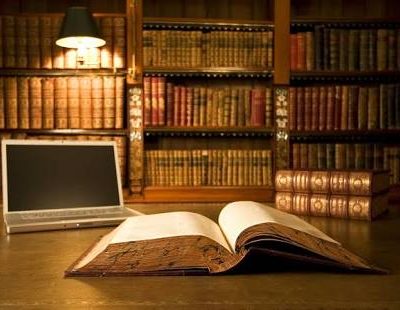行政事件訴訟法
(昭和三十七年五月十六日法律第百三十九号)
最終改正:平成二八年一一月二八日法律第八九号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十七年七月十七日法律第五十九号 (未施行)
行政事件訴訟法~行政事件訴訟の概要と種類
今回から、行政救済のうちの行政事件訴訟法を勉強します。行政不服審査法の中でも、時々顔を出していた行政事件訴訟は、行政活動に関連する紛争についての訴えに対して、裁判所が解決を図るための制度です。ここで、しっかり内容を把握し、もう一度行政不服審査法を読み直し比較すると、いっそう理解が深まると思います。
では、今日は①行政事件訴訟の概要、②行政事件訴訟の種類――を解説します。
過去問択一で選択肢を最後の2つから絞り切れないあなた!
重要条文を頭に叩きこもう!
Ⅰ.行政事件訴訟の概要
まず、行政事件訴訟の目的は、行政不服申立てと共通していて、
①私人の権利利益の保護
②行政運営における適法性の確保――です。
特に行政事件訴訟には、提訴者自身の権利利益と関わらない資格での訴えの提起が可能な、客観訴訟が存在することが大きな特徴です。提訴者自身の権利利益が侵害されたことを主張しなくても訴えが認められるので、目的は具体的・個人的な救済ではなく、一般的・客観的な行政に関わる法秩序の維持にあると言えます。
この客観訴訟の存在から、行政事件訴訟の目的が、個人の権利救済だけではなく、行政運営の適法性を確保する点をしっかり覚えてください。
法律による行政の原理を覚えていますか?
法律による行政の原理は行政に事前の統制を加えるものですが、いわば行政事件訴訟はこの法的統制を徹底させるため、事後的な審理を行うものだということになります。
また、行政作用法により行政主体はどう行動するかが規律されているのですが、これが守られない場合に適切な状態を回復させるのが行政争訟であるとも言えます。このことから、行政救済の場で主張が認められるのには、作用法のルールが破られていることが確認された場合と言えます。
ところで、行政事件訴訟と行政不服申立ての大きな違いは、判断権者が行政事件訴訟は裁判所であるという点です。しかし、行政事件訴訟は、裁判所が判断審査するため、違法性の判断しかされず、不当性の判断は対象外です。当不当の判断は行政裁量の枠内にあり、裁判所が介入できないからです。一方、口頭審理主義が採用されており、行政庁による不服審査に対して、迅速かつ慎重な審理がなされるという利点があります。
なお、行政事件訴訟法は、私人の権利救済の拡大という観点から、2004年に大幅に改正されました。改正のポイントは主に4つ、以下のとおりです。
①救済範囲の拡大:取消訴訟の原告適格の拡大、義務付け訴訟の法定、差止訴訟の決定、確認訴訟を当事者訴訟の一類型として明示
②審理の充実・促進:釈明処分の特則の制度の新設
③行政訴訟をより利用しやすく、分かりやすくするための仕組みの整備:抗告訴訟の被告適格の簡明化、抗告訴訟の管轄裁判所の拡大、出訴期間の延長、教示制度の新設
④本案裁決前における仮の救済制度の整備:執行停止の要件の緩和、仮の義務付け・仮の差止めの制度の新設
Ⅱ.行政事件訴訟の種類
行政事件訴訟の提起に当たり選択できる種類としては、取消訴訟、無効等確認訴訟、選挙訴訟、住民訴訟――など様々な種類があります。ここでは、これらを一つひとつ暗記するよりも、訴訟類型の分類を理解したうえで、各類型を分類の中に位置づけた方が理解しやすく覚えやすいと言えます。そこで、まず、行政事件訴訟の分類を勉強しましょう。
行政事件訴訟は大きく
①主観訴訟
②客観訴訟――に分けることができます。
1.主観訴訟
主観訴訟とは国民の権利利益の保護を目的とする訴訟で、法律に定める場合にのみ提起することができます(42条)。
そして、主観訴訟には、
①抗告訴訟
②当事者訴訟――があります。
このうち①の抗告訴訟は、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟と定義されます(3条1項)。つまり、公権力の行使に対して不服を述べるためのものですから、行政活動によって権利利益を侵害された場合に私人が救済を求める手段としては、中心的なものになります。
そして、抗告訴訟はさらに5つの形態に分かれます。その中心がa取消訴訟で、これはさらにァ処分の取消し訴え(3条2項)とィ裁決の取消しの訴え(3条3項)――に分かれます。
取消訴訟は、私人の権利救済のためには大変有効なものであり、古典的な訴訟類型です。このため次回からの各論では、取消訴訟に関しての勉強が中心になります。
それ以外の抗告訴訟の形態としては、b無効等確認の訴え(3条4項)、c不作為の違法確認の訴え(3条5項)という古典的な形態のほか、d義務付けの訴え(3条6項)、e差止めの訴え(3条7項)――という改正で付け加えられた新しい形態があります。
b無効等確認の訴えは、処分もしくは裁決の存否またはその効力の有無の確認を求める訴訟のことです。行政作用法の分野で、行政行為に重大かつ明白な違法が認められ、行政行為が無効になる場合を勉強しましたが、裁判で行政行為の無効を確かめるのが、無効等確認の訴えです。
c不作為の違法確認の訴えは、行政不服申立てのように申請に対する不作為が対象で、返答があった場合にはこの訴訟の対象とはなりません。ただ、不作為が違法であるか否かを確認するだけのものです。
一方、不作為に対して作為を命じるのはd義務付けの訴えになります。これは処分や裁決をすべき旨を命じることを求める訴えです。義務付け判決は、申請に対する不作為に限らず、それ以外の不作為に対しても提起することができます。
また、e差止めの訴えは、一定の処分または裁決をすべきでないにも関わらず、これがなされようとしている場合に、行政庁に対してその処分または裁決をしてはならない旨を命じることを求めるものです。
続いて②の当事者訴訟です。これは、当事者の法律関係を確認し、または形成する処分または裁決に関する訴訟と定義されます(4条)。抗告訴訟との決定的な違いは、先ほども説明したとおり、公権力の行使について争うか、自己の公法上の法律関係について争うかという点です。
当事者訴訟には、a形式的当事者訴訟、b実質的当事者訴訟――があります。
a形式的当事者訴訟とは、行政庁の処分または効力を争うものでありながら、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものと定義づけられます。つまり、法律により形式的には当事者訴訟の形をとりますが、その実質は抗告訴訟であるもののことです。このような形式があるのは、実質は抗告訴訟であり、行政庁の処分などを争うものであっても、当事者間で争わせた方が妥当な場合があるからです。
例えば、土地収用法133条2項で定められている補償額についての訴えでは、補償額を起業者と被収用者の間で争わせることになります。この例は、補償額を争うものである限り処分の効力に影響がないし、補償額とは売買における代金に相当するものなので、その適切な金額は当事者である起業者と被収用者との間で争わせた方がいいからです。
以上に対し、本来の当事者訴訟と言えるのが、b実質的当事者訴訟です。これは、まさに当事者の公法上の法律関係に関する訴訟のことで、例えば、公務員の地位確認訴訟、公法上の金銭債権の支払い請求訴訟、損失補償の請求訴訟がこれに当たります。
2.客観訴訟
客観訴訟とは行政活動の適法性の確保と客観的な法秩序の維持とを目的とする訴訟です。
客観訴訟には
①民衆訴訟
②機関訴訟――があります。
①の民衆訴訟は、国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、自己の法律上の利益に関わらない資格で提起するもの(5条)のことで、a住民訴訟、b選挙訴訟、c当選訴訟――がその例になります。
民衆訴訟は、原告適格が広く認められているので、法律だけでなく憲法に反する国家行為の是正を求めるのに役立ち、実際、憲法の判例の中には民衆訴訟の中で下されたものが数多くあります。
一方、②の機関訴訟とは国または公共団体の機関相互間における、権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟と定義づけられます(6条)。
例えば、重要な財産の処分には、議会の議決が必要との条例があるとして、今回の処分がそれに当たるか、それとも首長の判断だけでできるかの争いが起きることなどが挙げられます。この時にどちらが適切かを決するためには機関訴訟の判断を仰ぐことになります。このほか、国と地方公共団体の権限の行使についての争いとして、代執行訴訟があります。
このような行政機関内部における紛争は、自立権の問題として本来は行政庁自らが決すべきものとも言えます。しかし、両者が争い、決着がつかない場合には、公平な第三者の判断を求めることが適切なことがあるので、法律上、裁判所への出訴が可能とされたものです。
行政事件訴訟法~取消訴訟の機能と要件
行政事件訴訟の概要と類型を前回にお話ししましたが、今回からは、一つひとつの類型を見ていくことにします。
今日は、行政事件訴訟の中心である取消訴訟について、①取消訴訟の機能と他の行政争訟の手続きとの関係、②取消訴訟の要件――について解説します。
過去問択一で選択肢を最後の2つから絞り切れないあなた!
重要条文を頭に叩きこもう!
Ⅰ.取消訴訟の機能と他の行政争訟手続きとの関係
主観訴訟の一つである抗告訴訟、さらにその一つであるの取消訴訟は他の抗告訴訟と同様に、国民の権利の救済だけでなく、法治国家原理の担保という機能を有しています。
また、取消訴訟の機能をさらに細かく、
①原状回復
②適法性維持
③第三者との関係も含めて法律関係を合一にすること
④違法な行政活動の差止め
⑤行政庁に再度の考慮を促すこと
⑥処分の反復を防止すること――などと分類することも可能です。
しかし、これらは、国民の権利の救済と法治国家原理の担保に集約できると言えます。
ここで、取消訴訟と不服申立ての関係をもう一度整理しておきます。すでに説明したのが、自由選択主義です。審査請求できる場合でも処分の取消しの訴えが提起できるのでしたね(8条1項)。
例外は、不服申立前置主義で、法律に不服申立ての先行を要求する定めがある場合でした(8条1項但し書)。
それを踏まえたうえで問題となるのが、取消訴訟と審査請求の競合した場合です。実は法律上、同一の処分について取消訴訟と審査請求とは独立しているので、いずれでも選べるだけでなく、いずれも共にすることも可能です。しかし、双方同時になされたときは、審査請求の裁決があるまで裁判所は訴訟を中止することができます(8条3項)。それは、裁判所と審査庁の審理が並行して行われるのは無駄であるだけでなく、まずは、専門知識がある行政庁による迅速な解決が望ましいと言えるからです。
また、訴訟の中止中に取消しの裁決があったときは、審理をする意味がなく訴えの利益がなくなるので、訴えは却下となります。
これに対して、審査請求の裁決の前に裁判所による取消しの判決が確定した場合には、取消判決の形成力によって処分の効力がなくなります。この場合、関係行政庁は判決に拘束され、判決に対応する措置を採らなければならなくなります(32条1項、33条1項)。
ところで、取消訴訟は、
①処分の取消しの訴え
②裁決の取消しの訴え――に分類することができます。
①の処分の取消しの訴えとは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為の取消しを求める訴訟のことです(3条2項)。
一方、②裁決の取消しの訴えとは、審査請求・異議申立てその他の不服申立てに対する行政庁の裁決・決定その他の行為の取消しを求める訴訟を言います(3条3項)。
裁決・決定などの取消しの訴えでは原処分主義がとられ、裁決の取消しの訴えでは、処分の違法を理由として取消しを求めることができません(10条2項)。
仮に、処分の取消しの訴えと裁決の取消しの訴えとが別々に並行して提起され、いずれの訴えにおいても処分の違法について審理された場合は、いずれを先に審理するか、裁決が違法となったら処分の効力がどうなるか――などの問題が生じて混乱するおそれがあります。
そこで、裁決の取消しの訴えでは、裁決の手続きに違法があったなどの裁決固有の違法のみを主張できることとし、処分に関する違法の主張は処分の取消しの訴えで集中させるのが原処分主義です。
なお、特別な法の定めがある場合には、例外として裁決に対してのみ出訴が認められる裁決主義がとられることがあります。
例えば、弁護士から弁護士への懲戒に関する弁護士法61条2項や、特許庁の審判に関する特許法178条6項などがその例で、裁決に実質的な最終処分の性質があるというのがその趣旨です。
仮に、このようなルールを知らないで、処分の違法を主張する際に裁決の取消訴訟を起こしてしまった場合、この訴えに処分の取消しの訴えを合わせてすることに、16条2項の被告の同意はいりません。しかも、処分の取消しの訴えも裁決の取消しの訴えを提起したときに提起したものと見なされます(20条)。つまり、誤って裁決の取消しの訴えを起こした人も救済される――というわけです。
Ⅱ.取消訴訟の要件
取消訴訟における要件=訴訟要件は、訴えが適法であるために必要な条件です。これを欠く訴えは不適法なものとして却下されます。
訴訟要件には、まず特別の法律の定めがあるときは審査請求の前置が求められますが、それ以外の一般的な要件は次の6つです。
①処分性
②原告適格
③訴えの客観的利益(狭義の訴えの利益)
④被告適格
⑤出訴期間
⑥裁判所の管轄に属することなど
1.処分性(取消訴訟の対象)
①の処分性とは、取消しの対象になる行政活動に処分性が認められること、つまり、取消しの対象は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に限るということです。具体的には、許可、認可、下命、禁止――などがこれに当たります。
一方、行政行為の中でも公証や通知は、必ずしも新たな権利変動を発生させるものではないので処分性が認められるとは限らないとされています。しかし、判例では、通知のうち、これに引き続き確実に処分がなされる代執行の戒告などについては、通知の時点で争わせる必要性が高いこととも併せて処分性を認めています。
行政行為のうちでも通達などの行政の内部行為、行政指導などの非権力的な事実行為については原則として処分性は否定されます。
しかし、判例は例外を認めています。通達では、その通達が
①国民の権利利益に重大なかかわりを持ち、その影響が外部に及んで国民の権利義務に変動をきたすこと
②通達を争わせなければ権利救済がまっとうできないこと――などの条件が整う場合には処分性を肯定できるとしています。
また、行政指導についても、指導に従わない場合、相当程度の確実性をもって国民に重大な不利益がおよぶおそれがある場合には、例外的に処分性を認め、取消訴訟の対象としています。
事実行為や行政計画の処分性についても意見が分かれるところです。判例を見てみると、処分性については国民の権利義務を一方的に形成ないし確認する法律効果を伴うものか(=権力性)、その行為が当事者の権利義務を最終的に決定する終局段階のものと言えるか(=成熟性)という2点から、総合的に判断していると言えます。しかし、国民が一方的に実質的不利益を受け、しかもその行為の取消しのほかに適切な救済手段がない場合には、処分性を緩和したり、弾力的に運用し、処分性を肯定する傾向にあると言えます。
判例においての処分性の有無の判断を下表にまとめましたので、参考にしてください。
2.原告適格
次に、取消訴訟を提訴するにも取消しの対象となる処分との関係で、提訴する資格が必要です。これを②原告適格と言います。
具体的には、法律上の利益がある者のみが提訴できます(9条1項)。つまり、取消訴訟は救済の必要がある本人しか提訴できないということです。
ところで、原告に法律上の利益が認められるかどうかは、どう判断するのでしょうか?
判例は、法律上の利益とは法律上保護された利益、すなわち当該行政処分の根拠となる法規が保護した一定の私人の利益のこととしています。
言い換えると、処分の根拠になる法律が確保しようとしている利益の中に、原告が害されたと主張する利益が含まれていれば、原告に法律上の利益が認められるということです。ここで、処分の根拠になる法律は、公共の利益を確保するために行政に権限を与えると同時に、国民の利益を守るため行政行為を規制するものだったことを思い出してください。
このように法律上の利益が原告に認められるかどうかは、法律を基準として判断できるので明確であると言えます。しかし、反面、原告適格が認められる範囲が法律によって限定されるということは、立法の不備により、救済の必要がある場合に取消訴訟の対象から外れてしまうおそれも出てきます。
そこで、2004年の行政事件訴訟法の改正では、9条2項に法律上の利益の解釈規定を置くことで、原告適格の実質的拡大が図られました。そこには、処分または裁決の相手方以外の者、つまり第三者が法律上の利益を有するかどうかについて規定しています。ポイントは4つ、以下のとおりです。
①当該法令の趣旨及び目的
②当該処分において考慮されるべき利益の内容および性質
③当該法令と目的を共通にする関係法令の趣旨及び目的
④当該処分または裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容および性質ならびにこれが害される態様および程度
①の当該法令の趣旨及び目的、②の当該処分において考慮されるべき利益の内容および性質――が考慮されるのは、裁判所が処分または裁決の根拠となる法規の文言を重視した形式的判断を行うことにより、原告適格が狭められることを防ぐものです。
③の当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨および目的も参酌されるのは、根拠法令の文言のみに着目した解釈をすると、法令関係の趣旨目的が勘案されず、原告適格が狭く解釈されるからです。
④についても、原告適格を広く解釈するためです。
具体例は、判例をまとめた下表で確認してください。
☆原告適格を肯定した判例
☆原告適格を否定した判例
3.狭義の訴えの利益
狭義の訴えの利益とは、訴訟を維持する客観的事情・実益のことです。前述の処分性や原告適格とも存否の判断が難しいものでしたが、狭義の訴えの利益についても判断が難しいと言えます。
訴訟は当事者に現実的な救済を与えることを目的として、判決により侵害されていた権利や地位が回復されるものでなければ、訴えの利益を欠き却下判決が下されるのが原則です。ただし、原状回復が社会通念上不可能=訴えの利益がなくなるというわけではありません。
訴えの利益がない例としては、すでに行政庁が取消した処分、例えば、課税の減額再更正などは納税者に不利益がないので訴えの利益がないと言えます。
また、訴えの開始時において訴えの利益が認められていたのに、事情判決により後から訴えの利益が消滅することも問題となります。
これらの判例については、下表にまとめましたので個々によく確認してください。
4.被告適格
原則として、処分の取消しの訴えは処分をした行政庁の所属する国または公共団体を、裁決の取消しの訴えは裁決をした行政庁の所属する国または公共団体を被告として提起しなければなりません(11条1項各号)。その理由は、私人がどの行政庁を被告とすべきか調べたり、誤った行政庁を相手として提訴しやり直している間に、出訴期間が過ぎてしまうのを防ぐためです。
また、処分や裁決をした行政庁がいずれの行政主体にも所属しない場合(たとえば弁護士会など)には、当該行政庁を被告として提訴します(11条2項)。さらに、被告とすべき行政主体または行政庁がない場合は、当該処分または裁決に係る事務の帰属する行政主体を被告として提訴します(11条3項)。
5.出訴期間
訴えが適法であるというためには、出訴期間が遵守されることも必要です。処分や裁決の効力を長時間未確定にしておくのは不当であるとして、一定の期間を経過した行政行為には不可争力が与えられていることに対応した要件です。
具体的には、処分または裁決があったことを知った日から6カ月(14条1項)、処分または裁決の日から1年(同条2項)を経過しないことが原則ですが、正当な理由があるときはこの限りではありません。正当な理由がある場合とは、災害、病気・けが、教示が誤った場合――などが考えられます。
また、審査請求など行政不服申立てを経た時の出訴期間は、裁決・決定があったことを知った日または裁決・決定があった日から起算されます(14条3項)。審査請求のため行政事件訴訟の出訴期間が経過し、司法的救済が受けられなくなることを防ぐためです。
6.裁判管轄
出訴は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所または処分等をした行政庁の所在地を管轄する地方裁判所にします(12条1項)。原則として、事物管轄は第一審は地方裁判所が、土地管轄は被告行政庁の所在地にある裁判所に行います。
ただし、特則があります。
原告の出訴を容易にし、証拠調べ等の便宜を図ることを狙い、不動産または特定の場所に係る処分または裁決に係る処分は、不動産または場所の裁判所に管轄が認められます。
また、取消訴訟については、事案の処理に当たった下級行政機関の所在地の裁判所にも管轄が認められます。
そして、国を被告とする取消訴訟は、原告所在地を管轄する高等裁判所所在地の地方裁判所にも管轄が認められます。これは、国を被告とする取消訴訟は、上記の原則によるとどうしても東京地裁が管轄になることが多くなるので、地方在住者による提訴の便宜を図るためです。
行政事件訴訟法~取消訴訟の審理と判決
取消訴訟の審理は、まず、前回の6つの要件の確認から始まります。今日は、行政訴訟事件の審理と判決について、①取消訴訟の審理手続き、②執行停止の制度、③判決の種類と効力――の順に解説します。
Ⅰ.取消訴訟の審理手続き
取消訴訟が提起されると、まず裁判所は訴訟要件の有無について審理します。これを要件審理と言います。取消訴訟の要件に不備があることが判明した場合、訴えに対して補正を命じ、これに従わない場合は内容を審理することなく訴えを却下します。
訴訟要件に問題がない、あるいは補正された場合は、本案の審理が開始されます。行政事件訴訟法は、審理について多くの規定がなされていないので、行政事件としての本質に反しない限り民事訴訟についての規定が準用されます。
民事訴訟の審理に関する基本原理のうち、弁論主義は事案解明に関する原理として行政事件訴訟にも適用されます。しかし、取消訴訟では公益実現と関係する行政行為の適法性が審理の対象となるため、真実発見の必要性が高いのでいくつかの特則があります。
特則としての大きなものは次の2つです。
①職権証拠調べ
②釈明処分
まず、①の職権証拠調べは、必要に応じて裁判所の裁量で証拠の収集ができるとするものです(24条)。行政事件訴訟でも原則は当事者主義(弁論主義)が採用されます。しかし、当事者の主張する事実の証拠が不十分で裁判所が心証を形成できないときは、職権で証拠を調べることが許されているのです。ただし、判例によれば、当事者の提出した証拠だけで十分な心証が得られる場合は、必要ないので職権証拠調べはする必要がありません。
また、行政不服申立てでは行政庁には職権探知(当事者が主張しない事実を取り上げること)が認められていましたが、行政事件訴訟では基本を民事訴訟としていることから、条文の定めがない扱いは認められないので、当事者が主張しない事実まで探査する職権探査は認められないとするのが判例です。
同時に、当事者主義の建前をまったく無視することもできないので、裁判所による職権証拠調べの結果について、当事者の意見を聞くことが必要です。
次に②の釈明処分として、行政庁に対して資料の提出を求めることもできます(23条2項)。資料とは裁決の記録や処分の理由を明らかにするためのものです。
これから、少し応用編を扱います。
まず、相互に関連する訴訟が提起された場合、別々に審理することは当事者や裁判所は、審理の重複する負担を負うことになり、裁判の抵触も考えられるので、関連請求に係る訴えは取消訴訟と併合できます。
併合は主に4つの場合があります。
a請求の客観的併合
b共同訴訟
c第三者による請求の追加的併合
d原告による請求の追加的併合
aの請求の客観的併合とは、原告が取消訴訟の提起に当たり、関連請求に係る訴えを取消訴訟に併合することです(16条)。ただし、この場合の被告は取消訴訟の被告と同じ行政主体であることが必要です。
bの共同訴訟とは、複数の原告が請求する場合または複数の原告に対して請求する場合、取消訴訟の関連の請求であるときは、併合して訴えを提起することが可能というものです(17条)。
cの第三者による請求の追加的併合とは、第三者が取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまでに、訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えを取消訴訟に追加的に併合できることです(18条)。
dの原告による請求の追加的併合とは、原告が取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまでに関連請求に係る訴えを追加的に併合し提起することができることです(19条)。
次に、訴えが変更される場合を見てみましょう。
裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分、または裁決に係る事務の帰属する国または公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当と認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまでに、原告の申立てにより、決定をもって訴えの変更を許すことができます(21条1項)。
この目的は訴訟の効果的運営と原告の負担軽減です。
さらに、係属中の訴訟に当事者以外の第三者が自己の権利利益を擁護するために参加することができ、これを訴訟参加と言います。
裁判所は、訴訟の結果により権利を侵害される第三者があるときは、当事者またはその第三者の申立て、または職権で、決定をもって第三者を訴訟に参加させることができます(22条1項)。また、他の行政庁を訴訟に参加させることが必要と認めるときは、当事者もしくは行政庁の申立てまたは職権で、決定をもって、行政庁を訴訟に参加させることができます。(23条1項)。
Ⅱ.執行停止の制度
行政事件訴訟でも、行政不服申立てと同じく審理の開始により処分が続行される場合もありますが、停止される場合もあります。
行政事件訴訟も執行停止されないのが原則ですので、一定の条件が満たされた場合にだけ執行停止制度があります。これは、行政不服申立てと同様に、濫訴を予防し、行政の円滑な運営を確保するためです。これらのことは25条1項に「処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続きの続行を妨げない」と規定されています。また、行政庁の処分、その他公権力の行使に当たる行為は、民事保全法44条に規定する仮処分をすることもできません。
そこで、代償措置として、処分の効力、執行、手続きの全部または一部を停止させる執行停止制度が設けられているのです。これは、執行不停止の原則の例外です。
ポイントをまずお話しすると、執行停止ができるのは行政不服申立てにおける必要的執行停止と類似の要件を満たしている場合です。裁判所には行政権がないので、行政裁量は認められず行政活動への介入も最小限でと考えられているからです。
また、同じ理由で、執行の一部または全部の停止しかできず、それ以外の処分もできないということも覚えておいてください。
では、要件から見ていくことにしましょう。要件は25条に定められ、まとめると次のとおりです。
①原告、利害関係を有する第三者からの申立てがあること
②重大な損害を受けるために緊急の必要があること
③執行停止によって公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないこと
④本案について理由がないと見えないこと
まず、①の執行の停止には訴えの提起が必要です。民事保全のような提訴の前の執行停止制度はありません。そして、執行停止には申立てが必要です。つまり、行政不服申立てと異なり職権による執行停止はありません。
執行停止の要件として重要なのが、②の処分等により生ずる重大な損害を避けるための緊急の必要があるということです。重大かつ緊急の場合には、処分の執行等により原状回復が不可能となり、勝訴の意味が失われるおそれが認められることに執行停止ができる理由があります。
ここでは、重大な損害=償うことのできない(回復困難な)損害と比較すると穏やかな要件であることに注意が必要です。
重大かつ緊急の要件は、事案に照らして一体的に判断されます。
また、重大かつ緊急の要件をみたすかの判断に当たっては、
a損害の回復の困難の程度
b損害の性質・程度
c処分の内容・性質――を考慮するとされています。
a~cの要件が整う場合とは、行政処分により取消訴訟を待っていれば事業再建の機会が失われる場合(損害回復の困難性が認められる)、代わりを求める時間的余裕がない場合、情報公開条例に基づく開示決定の取消しを求める場合(情報が公開されれば、回復されるべき利益が失われる)――などが挙げられます。
執行停止の申立ての前に執行が完了してしまえば、執行停止は認められません。停止をしても原告が救済されることが何にもないからです。
以上の要件が整うことを申立人が立証できた場合には、原則として執行の停止ができます。ただし、次のように行政主体が主張し、それが明らかとなった場合は、執行停止ができません。これは、③④の要件に当たります。
まず③の執行停止によって公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある場合は、執行停止はされません。執行を停止してしまうことで、行政行為が確保しようとしている利益が害され、処分が違法でなかった場合に取り返しがつかない結果となるからです。つまり、執行の停止により確保される利益以上の不利益の発生が予想される場合、執行停止はできないわけです。
この例として、集会やデモ行進の不許可、土地収用に対する執行停止の申立てなどが挙げられます。
また、当然ですが、救済する必要がないので④本案について理由がないと見える場合も執行停止がなされません。
次に執行停止の手続きについてお話しします。
執行停止は、原告、利害関係(申立人適格)を有する第三者からの申立てをきっかけに審理され、決定によって判断されます。申立人の主張を認める決定により処分の効力、処分の執行または手続きの続行の全部または一部が停止されます。
また、執行停止には、
①効力の停止
②執行の停止
③手続きの続行の停止――があります。
①の効力の停止は処分がなかった状態の回復、②の執行の停止は強制手段によることの停止、③の手続きの続行の停止は後続処分の停止です。③→②→①の順に効力が強くなります。そして、法令では、他の手段によって目的が達成できる場合には、執行の停止ができないとしているので、③で目的が達成できれば②によることはできません。また、②で目的が達成できれば①によることはできないのです。
ということは、例えば農地の売渡しを受けた債権者には元所有者に対しての農地立ち入り禁止の仮処分の効力は残ります。
決定に不服がある者は、高等裁判所への即時抗告ができます(25条7項)。即時抗告とは、一定の不変期間内(この場合1週間)にしなければならない抗告のことです。ただし、決定された執行は停止されません(25条8項)。執行停止の決定があった場合は、即時抗告だからといって停止を免れることはできないわけです。
また、執行停止の後も執行停止の理由が消滅するなど事情が変更した場合には、裁判所は行政庁の申立てにより執行停止の決定を取消すことができます(26条1項)。停止により確保すべき利益が失われた場合には公益の確保を優先するために柔軟な対応ができる仕組みになっています。
裁判所による執行の停止ができない場合に、内閣総理大臣の異議の制度があります(27条)。異議が申し述べられた場合、裁判所は執行停止をすることができず、または執行停止の決定を取消さなければなりません。
裁判所は行政権の枠外ですから、行政上の利益の確保について十分な判断ができない可能性があるので、行政判断の適正が害され、公共の福祉が失われるのを防ぐことが目的です。異議は、執行停止決定の前後を問わず述べることができます(27条1項)。
しかし、異議の制度にも制限があります。異議を述べるのはやむを得ない場合に限ります。また、その際には執行の停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるという事情を示す(理由を付す)必要があります。恣意的な制度の運用を防ぎ、慎重に異議するかどうかを判断させる趣旨です。
さらに、異議を述べた場合は、内閣総理大臣は次の通常国会において国会に報告する必要があります。民主的コントロールを通じて、行政権の濫用を防ぐ趣旨です。
この内閣総理大臣の異議の制度は、行政不服申立てにはない、行政事件訴訟特有の制度です。
Ⅲ.判決の種類と効力
審理が終結すると判決が下されます。訴訟手続は民事訴訟と同様に、取下げ、放棄・認諾、和解によっても終了しますが、ここでは、判決による終了についてお話しします。
まず、判決の種類は3つ、①却下、②棄却、③認容――です。
①の却下は、必要な要件が整わない場合に、本来の審理を拒絶する判決です。原告の請求が認められたわけではありませんが、棄却とは異なり、処分が適法と判断されたわけでもありません。
次に②の棄却の判決は、請求に理由がないとするものです。この場合、原則として、処分の効力は維持され、かつ処分が適法であることが確定します。しかし、処分の効力が維持されるものの処分は違法であると確定する場合もあります。これが、事情判決で、行政不服申立てでも取り上げました。
いったん行政行為がなされると、これを基礎に現状が変更されることがありますが、引き続き新たな事実的・法律的秩序が形成されることになります。
例えば、土地改良事業が施行されたり、土地の区画整理計画が策定され、実施されて、現状が変更される場合です。この場合に、行政行為を取消して元の状況に回復すすることは大変な手間と費用がかかり、また合理的な土地利用ができる状況を元に戻してしまうことは現実的ではないので、処分が適法でないと確定されても、効力は維持されます。
このとき、処分(または裁決)が違法であることを宣言しなければならないものとされています(31条)。この宣言により、後に原告が国家賠償請求による救済を求めた場合に、請求が認められやすくなることが期待できます。
また、裁判所は相当と認めるとき、最終的な判決前に判決をもって処分が違法であると宣言することができます(31条2項)。これは、中間違法宣言判決と言い、違法であるという判断が終局判決で変更されることはありません。そこで、この宣言によって行政庁が違法であることを覚悟して、損害賠償など原告に対する救済手段を採ることを促進する効果を狙ったものです。また、あえて、中間違法宣言をするということは、事情判決になる可能性判断をさせることにつながるとも考えられます。つまり、両者に和解を促すことにもなるのです。
さて、③の認容の判決です。取消訴訟の場合は、取消判決、つまり全部または一部を認容したら、これに応じて処分または裁決の全部または一部を取消す判決をすることになります。この場合、判決の直後の意味としては、行政庁の行為が違法であり、処分の効力を否定するというものにすぎません。関係行政庁に一定の処分または裁決をすべきという意味はありませんし、その旨の給付判決をすることもできません。
しかし、取消訴訟は関係行政庁を拘束する効力が発生するので、関係行政庁は判決の趣旨に沿った措置を採る必要があります(33条1項、2項、3項)。つまり、改めて取消判決の趣旨に従った処分や裁決をしなければならないということです。
認容の判断が下されるのには、当然処分が違法との判断がなされる必要があるのですが、行政処分から判決までの間に法令が制定・改廃や事実状態が変動する場合、裁判所の違法判断は、いつの時点で行うのでしょうか?
例えば、建築確認の拒否がなされた時点では拒否に理由がなかったけれど、その後法改正がされたり、建物を建てようとする地区が建築制限の指定を受けたりして、建築確認を拒否すべき状況になることがあります。この場合に拒否の時点を基準にするのか、判決の時点を基準にするのかは、大きな問題点です。
判例によれば、基準の時点は、処分当時の法令・事実を前提とするとしています。これは、取消訴訟は行政処分の事後審査で、行政行為が行われた時点で違法か適法かを審査する制度だからです。
ところで、判決が下され確定すると、行政事件訴訟の目的を達成すべく、次のような様々な効力が発生します。
①既判力
②形成力
③拘束力
①の既判力とは、当事者は判決の内容と矛盾する主張はできず、裁判所も矛盾する裁判ができなくなるという効力です。
取消訴訟の場合、裁判所の判断対象である訴訟物は処分の違法性一般とされていることに対応する効力です。この結果、取消判決がなされた場合、被告行政庁は、次のステップである国家賠償請求訴訟でも当該処分が適法である旨の主張・判断はできなくなります。
一方、棄却判決の場合は、当該処分が適法であると確定するので、原告が後の国家賠償請求訴訟等で処分の違法性を主張することはできなくなります。
しかし、この場合にも、行政庁が棄却判決の対象となった処分を撤回することは許されます。行政庁が処分を不当と考えた場合や、後の事情の変更で処分の効力を否定するのが適当だと判断できるなら、公益の確保と国民の利益救済のいずれの観点からも効力を維持する必要がないからです。
次に②の形成力です。特に取消判決が確定した場合には、当該処分の効力は当初から失われることになります。また、形成力の特徴は、第三者にも効力が及ぶことです(32条1項)。
この結果、例えば農地の買収の取消しは、農地の転得者にも及びます。そのため、売渡しを受けた人は、農地返還義務を負うことになります。このような場合に第三者に利益確保の機会を与えるために第三者には訴訟参加の機会が与えられています(22条1項)。また、判決効を否定するため、再審の訴えの提起も許されています(34条)。
そして、もう一つ、取消判決に与えられる重要な効力に③拘束力があります。これは、取消判決の趣旨に行政庁は従って行動することが義務付けられるという効力です(33条)。
取消判決は、処分の違法性を確認しつつ、処分の効力を否定する意味がありますが、処分の効力が否定された場合に、改めてまったく同じ処分が繰り返されたらどうなるでしょうか? いつまでたってもキリがない、言い換えればいつまでたっても原告の救済ができません。その救済が必要というのが取消訴訟の趣旨であったはずなので、訴訟の実効性を確保するために、拘束力が認められているのです。
この結果、行政庁は、同一人に対して同一の処分をすることができません(反復禁止効)。
また、行政庁には、判決の趣旨に従い、改めて措置をとるべき義務が発生することがあります。
例えば、申請の却下・棄却や、審査請求の却下・棄却をしたところ、これらが取消された場合、処分や裁決をやり直す必要が出てきます。このときは、判断がまだなされていない状態になります。このことは、私人が改めて申請や審査請求をしなくても、行政庁は処分や裁決をしなければならないということです。この場合には、反復禁止効も働くので、行政庁は同じ理由で申請や審査請求の却下・棄却はできません。
さらに、違法状態を除去する義務も発生します。例えば、租税賦課処分が取消された場合、後行処分である滞納処分も取消す義務が発生します。
行政事件訴訟法~その他の抗告訴訟
行政事件訴訟法の最終回です。行政事件訴訟には、取消訴訟以外にも、無効等確認の訴えや不作為の違法確認の訴えをはじめとする様々な類型があります。
今回は、①無効等確認の訴え、②不作為の違法確認の訴え、③義務付け訴訟、④差止め訴訟、⑤仮の救済制度――とお話ししていきます。
Ⅰ.無効等確認の訴え
無効等確認の訴えは、行政庁の処分もしくは裁決の存否またはその効力の有無の確認を求める訴訟です(3条4項)。無効等確認の訴えは審査請求を前置する必要がなく、また、出訴期間の定めもありません。そのほかの取消訴訟に関する規定は、ほとんど準用されます。
また、無効等確認の訴えの要件は、原告適格について独特の定めが置かれています。
第36条(無効等確認の訴えの原告適格)
無効等確認の訴えは、当該処分または裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者※1その他当該処分または裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分もしくは裁決の存否またはその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない者※2に限り、提起することができる。
判例によれば、無効等確認の訴えは、※1か※2のどちらかの条件が整えば提起できるとされています。※1を①予防的無効確認訴訟、※2を②補充的無効確認訴訟と言います。
まず、①の予防的無効確認訴訟から説明します。無効な行政行為と判断されても、処分そのものが形式的に存在しているように見えることがあります。予防的無効確認訴訟の目的は、存在するように見える処分に基づいた後続処分や執行処分が行われることを予防することです。相続処分や執行処分がまだ存在していない時点で取消訴訟の形式をとることはできませんから、予防的確認訴訟の実益はここにあると言えます。
一方、②の補充的無効確認訴訟は、現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限って、提訴が認められるものです。現在の法律関係に関する訴えとは、処分が無効であることを先決問題とする訴えのことで、例えば、懲戒免職が無効であることを前提として退職手当の支払いを求める訴えや、土地収用裁決が無効であることを前提として起業者の登記の抹消や土地の返還を求める訴え――などが挙げられます。
これらは、公務員関係は当事者訴訟、土地の返還は民事訴訟の形態で実施されます。なお、民事訴訟の中で行政処分の効力が争われる訴訟を争点訴訟(45条)と呼び、行政事件訴訟法の職権証拠調べや訴訟参加などの若干の定めが準用されます。
以上の事例は、他に提訴の手段が存在しない場合でした。しかし、判例では、他の手段が存在しても、処分の無効確認の訴えの方が権利救済のために直接的で適切であると判断される場合には、提起が認められています。
例えば、土地区画整理による換地処分が無効という場合、処分を無効として土地所有権の存在確認の訴えという民事訴訟のよることも考えられます。しかし、換地処分は単に当事者間だけの問題ではなく、複数の当事者が連鎖して関連するものです。また、換地処分を無効とする理由が、自己が取得する土地が不利であるという場合には、土地の所有権を主張することでは意味を成しません。つまり、民事訴訟の形で所有権の確認をしても何ら救済にはならないのです。そこで、換地処分の無効を主張することこそが、原告の救済の手段として適切であると言えるのです。
このほか、原子炉設置許可処分について、別に原子炉の設置または運転の差止めを求める民事訴訟を現に提訴し、争っていても設置許可処分の無効を争うことは可能との判例も存在します。
なお、判例では、ある処分に重大かつ明白な違法があることの主張および証明の責任は原告が負うとされています。
Ⅱ.不作為の違法確認の訴え
不作為の違法確認の訴えとは、行政庁が相当の期間内に何らかの処分または裁決をすべきにもかかわらず、これをしない場合に提起するもので、処分または裁決をされないことが違法かどうかを確認することが目的です。
ただし、すべての不作為についての違法の確認を求めることができるのではなく、行政不服申立てと同じく申請をしたことが必要です。しかも法律上、申請はこれをすることが認められている者に限られますから、法令に基づく申請をした者に限り提訴できるわけです。申請を伴わない場合(職権による行為についての不作為)は、次に解説する義務付けの訴えによって不服を主張します。
不作為の違法確認の訴えは、不作為が続く限り認められるので、出訴期間が存在しません。また、処分や裁決が存在しないので、執行停止の余地がなく、執行停止制度の適用もありません。
Ⅲ.義務付けの訴え
不作為の違法の訴えは、行政庁が義務に違反してなすべきことをしない状態にあることを明らかにするものなので権利救済の実効性は弱いと言えます。かつては、行政活動をするかしないかという問題は行政裁量に属するから、裁判所が介入をすべきでないという考え方が根強くありましたが、行政が間違った行為をした場合に国民を救済する必要性から生まれたのが不作為の違法確認という訴訟形態です。法律上の義務に違反する行政庁に法律を遵守するよう命じることは当然司法権の及ぶ範囲と言えるのです。
そこで、従来からの行政の義務違反に対し、必要な行為をするよう命じることを立法化したものが、③の義務付けの訴え(3条6項)です。
義務付けの訴えには2つの類型があります。
a行政庁が一定の処分をすべきであるにも関わらずこれがされない場合(1号)
b行政庁に対し法令に基づく申請または審査請求がされた結果、求められた処分または裁決をするべきなのにこれがされない場合(2号)
aの1号訴訟を直接型義務付け訴訟とよびます。非申請型義務付け訴訟と言ってもよいでしょう。
例えば、環境に悪影響を及ぼしている事業者に対して、改善命令を出すなどの行政規制権限の発動を求める訴えがこれに当たります。
また、義務付けの訴えは、訴訟要件と本案勝訴要件の両方に法の定めが必要なことも注目すべき点です。
まず、訴訟要件は、
ァ重大な損害を生じるおそれ(重大性)
ィ他に適当な方法がない(補充性)――の2つです。
ァの重大性は、執行停止の要件と同じです。執行停止を認めるべきであるような限られた場合にのみ義務付けの訴えが提起できるということです。
ィの補充性とは、行政過程に特別な救済の方法が設けられていないということです。
義務付け訴訟の要件で執行停止の要件と異なる点は、義務付け訴訟には緊急性が求められていない点です。
訴えに当たっては法律の利益が認められることも必要で、これは他の抗告訴訟と同様です。
また、義務付けを命じる判決がくだされるにも、要件が必要です。
まず第一が、
①処分をすべきであることが根拠となる法令の規定が明らかなこと、つまり明白性の要件が満たされなければなりません。
または、
②処分をしないことが裁量権の範囲を超えたり、裁量権の濫用に当たる