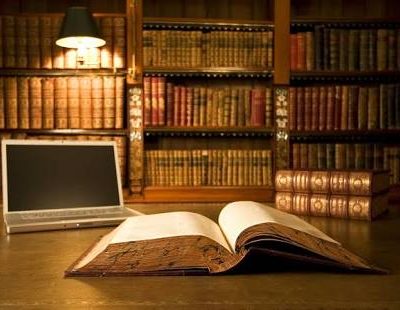行政行為は10に分類できることを前回お話ししましたが、今回は、行政行為の効力である①公定力、②公定力の限界、③行政行為のその他の効力――についてお話しします。
Ⅰ.公定力
行政行為の効力には、まず、当然に国民に権利を与えたり義務を発生させたりする効力がありますが、これだけでは民法の法律行為と同じで、取立ててお話しするほどのものではありません。そこで、国や公共団体と国民間の法律関係における、行政行為の特殊な効果についてお話ししたいと思います。
行政行為特有の効果としてまず挙げなければならないのが、公定力です。公定力とは、違法な行政行為でも、どんな人もその行政行為の効力を無視することはできない――という効力のことで、効力を否定するためには、取消し権限がある国家機関による取消しが必要です。行政行為の相手方が第三者や他の国家機関でも、もちろん効力を無視できませんし、違法な行政行為でも行為の効力が無視できないということは、違法でも有効として扱われるということです。
つまり、行政行為の拘束力を強要する力が公定力と言えます。
一般原則からすると違法な行為は無効なはずなのに、行政行為にこんな危険な効力を認めてよいのでしょうか?
答えは大丈夫、権限ある機関が取消せば、行政行為の効力も取消せます。言い換えれば、違法な行政行為も当然に有効ということではなく、効力を否定するには条件が必要であり、誰でも否定できるわけではないのが公定力です。
ここで、民法における取消しと行政行為の取消しを比べて見ます。民法の世界では、取消し得る行為は例外として決まっていて、取消権がある人が取消すまで効力が有効でした。あくまで、例外だったのです。一方、行政行為は、通常、取消し得る行為として扱われています。
この結果、例えば、農地について違法な買収処分が行われ、転売された場合、民法の世界なら、法律行為が無効である以上、物権的請求は返還が求められます。取消しも返還請求と同時に行えば足ります。
しかし、農地の違法な転売が行政行為だった場合、公定力働く結果、違法な処分も有効なままですから、所有権は転得者の下にあることになります。そこで、農地を取り返すためには、まず前提として不服申立て、取消訴訟――などの手段を用いて処分を取消しておく必要があります(詳しくは、行政救済法で解説します)。
では、一体なぜ行政行為がこのような特別な取扱いをされるのか考えましょう。
その理由の1つに、行政行為が違法かどうかの判定は難しいことが挙げられます。行政行為をするのは国や公共団体である行政庁です。行政庁には裁量が認められていましたね。この裁量の範囲にある場合は、例え不当であっても違法とはされません。そして、裁量の範囲の判断は非常に難しいのです。それは、行政行為が公益を確保するための特殊な行為だからです。
また、違法であれば誰でも行政行為を無効と主張できることにすると、誤解や私欲などに基づいて、有効な行政行為まで無効を主張する人が次々と出てくるおそれがあります。これでは、円滑に事務処理が進まず、行政行為の目的の達成が困難になることも、行政行為に公定力を認める理由の一つと言えます。
以上のことから、行政行為の目的達成のため、行政行為は権限ある国家機関が取消すまで一応効力を温存さするものとされていますが、単に効力を否定できないというだけです。したがって、決して違法な行政行為を適法としているというわけではありません。
言い換えれば、公定力とは効力を否定することに対して、法律で条件が付けられた結果、反射的に生じる効力です。
Ⅱ.公定力の限界
前述のように、公定力は違法な行政行為を適法と評価するものではありません。行政行為の効力が否定されなくでも目的は達成できることから、国家賠償請求や刑事裁判で行政行為の違法性を認定するだけなら、行政行為の取消しは必要ありません。
また、複数の行政行為の間には、先行処分が後行処分の準備行為にすぎないことがあります。
例えば、土地収用手続きにおける事業認定とそれに続く収用裁決は、事業認定がなければ収用裁決をすることができません。この場合における2つの行政行為の関係は、本来はそれぞれ別個の行為です。ですから、その効力は別個に考えるべきですが、実際は、事業認定が違法なら、あとに続く収用裁決の効力も認められません。
これを違法行為の承継と言い、前提とする行政行為が違法であることを理由に、その後の行為の効力を否定することが認められています。違法行為の承継の結果、違法と思える先行処分に公定力・不可争力があっても、それに関わらず、後行行為について争えることが可能になります。つまり、後行行為を争う訴訟で先行行為の違法性を認定できるわけです。
本来は、先行行為そのものを取消し訴訟などの然るべき手続きにより争うべきで、先行行為の取消手続の利用可能期間経過後には、もはや争えなくなる(不可争力)事案でも、違法行為の承継で、その例外を認めさせることが可能になります。すなわち、先行行為が公定力を理由に争えない場合に、後続処分を争う機会を広げて、国民の救済を図ることができます。
しかも、公定力は、行政行為が違法であることの判断が難しいことに対して認められたものなので、違法であることが誰の目からも明らかな場合は、公定力を発生させ無効の主張を制限することができないのは当然です。
したがって、瑕疵が重大かつ明白な行政行為に公定力は発生しません。後述する取消訴訟によって効力が争えなくなる不可争力も発生しません。
Ⅲ.行政行為のその他の効力
行政行為に認められる特殊な効力はまだまだあります。まず、前述に出てきた不可争力です。これは、一定の期間が経過すると行政行為に問題があっても、私人の側から行政行為の効力を争うことができなる――という効力のことです。
これは、一定の期間の経過によって行政行為の効力が然るべき手続きによっても否定できなくなることで、行政上の法律関係を早期に確定させるためのものです。後になってから行政行為が無効となって、それが前提で行われた他の行政行為に影響が出ることや、迅速に行政目的を達成するために必要なのが不可争力と言えます。
不可争力が発生した行政行為は、不服申立てによる取消しや取消訴訟による取消しができなくなります。
ただし、不可争力が発生したからといって、違法な行政行為がそのまま通用するわけではありません。過ちを改めるには、行政庁が職権で行政行為を取消し・撤回することは可能です。あくまで、私人である国民側から争えなくなるだけです。また、重大な瑕疵が認められるような無効な行政行為には不可争力は発生しません。
次に、自力執行力についてお話しします。行政行為には少なからず権力的な色彩が見られます。行政行為によって発生した義務を国民が履行しない場合、行政庁自らが義務者に対して強制執行をして、義務の内容を実現することができますが、このことを自力執行力と言います。私人なら、自力救済は禁止されますが、行政庁はそうではなく、義務の実現に裁判所を介する必要がありません。
自力執行力により裁判をする必要がないので、迅速に義務が実現し、行政目的を早期に実現できます。また、裁判所を介する必要がないので、裁判所の仕事の軽減にもつながります。
民主的コントロールが働くのか少し心配になってきますが、行政活動は法律を通して民主的にコントロールされていますし、行政庁には専門的知識もあります。そこで、私人が非常手段に出るのと異なって、やり過ぎや間違いが起こる可能性は低いと言えます。行政目的という公益の早期実現と天秤にかけて、特別な扱いが認められていると考えられます。
これにまつわるものとして、執行不停止の原則について少しお話しします。これは、行政行為に対する不服申立て・抗告訴訟を提起しても、原則として自力執行力は妨げられないという効力のことです。後で詳しく解説しますが、不服申立てが執行を妨害する手段として使われることを防止し、円滑で迅速な行政目的を達成するためのものです。これも公定力や不可争力と同じで、行政目的達成のため、特別に認められる原則の一つです。
ところで、自力執行力が発生する行政行為の特別なものに警察などによる捜査があります。これは、裁判所による令状は必要ですが、行政官自身による強制が認められています。このほかにも、職務質問などの行政警察活動は、公権力の行使としての行政活動そのものです。
ただし、自力執行力は、公定力や不可争力と異なり、行政行為に当然に与えられるものではありません。その性質上、下命・禁止などの義務を課す行政行為に限って発生します。また、このような行政行為なら何でも自力執行力が発生するわけではなく、法律による明文の根拠がある場合に限られます。
さらに、行政行為の特殊な効力として、不可変更力や実質確定力――のような一度なされた行為の変更が許されないとする効力があります。不可変更力とは、行政行為をした行政庁が自らこれを変更することが許されない効力です。実質確定力とは、ある行政行為が処分庁だけでなく上級行政庁や時として裁判所まで拘束する効力のことです。
行政行為は、行政庁が自由に取消しや撤回できるのが原則です。しかし、行政行為のうち特定の種類のものは取消しや撤回ができません。
特定の種類のものには、
①異議申立てに対する決定
②審査請求に対する裁決――などが挙げられ、紛争を終結に導くためのものです。それぞれの内容については、行政救済法のところで解説します。
紛争を終結に導くための行為に変更が許されないのは、事件の解決という行政行為の目的を達成するためです。
最後に、行政行為には、法律関係を変動させるほか様々な効力がありますが、その効力が発生するのは何時かということも重要です。基本的には民法と同じく到達主義が採られています。
今回は、行政行為についてしばしば問題となる行政裁量についてのお話です。今までの回にもしばしば登場しましたね。何となく、イメージはつかめていると思いますが、この回でしっかりマスターしましょう。
今回は「行政裁量とは何か」、次回は「裁量権の逸脱・濫用の判断基準」――と2回に分けてお話しします。
行政裁量とは、一言で言えば、行政行為を行うに際して法律により行政機関に認められた判断の余地のことです。
行政機関に裁量を認めることは、必ずしも良いことばかりではありません。行政機関は、歴史的に見ると国民の権利を侵害するおそれが強い機関と言えますので、法律によって行政機関を拘束した方が、国民の権利を守ることができるとの見方もできます。この考え方から導かれる行政の原則が法律による行政ですが、これを徹底するためには、行政には覊束行為、つまり裁量の余地がない行為だけを許すことにした方が良いということになります。
過去問択一で選択肢を最後の2つから絞り切れないあなた!
重要条文を頭に叩きこもう!
しかし、行政府に判断の余地を与えたから直ちに国民の権利が侵害されるとは限りませんし、法律以外でも、例えば国民の批判とか、議院内閣制による内閣へのコントロールなど、不当な行為を許さない力は、様々な形で存在するわけですから、法律ばかりに頼らなくても人権の保障は可能なわけです。
また、法律は改正に長時間かかるので、行政活動にすべての法律の根拠が必要とすると、そのルールが時代に合わなくなってきたときに素早い対応をすることができません。さらに、現代の複雑な社会においては、そもそもすべてを法律で規定し尽くすこと自体が無理と言えます。
現代では、行政に求められることは、ゴミの収集、子育て支援、老人や障害者福祉のような身近な問題から、外交・国防まで――と複雑多様であってその中には高度で専門的問題も出てきます。このような場合には、行政庁の知識と判断能力に期待する方が迅速かつ妥当な解決を期待でき、かえって国民の利益になると言えます。
そこで、行政をうまく実施するには、現場の判断を尊重することが望ましいことが少ないない――ということから、行政庁の自由な判断に従って判断する余地を認めたものが、行政裁量です。
次に、行政裁量に関わる行為について順を追って説明したいと思います。
まず、先ほど、裁量が認められない行為として覊束行為という言葉を使いましたが、これは裁量行為の対語といえる言葉です。つまり、法律が行政機関に政策的・行政的判断の余地を与えない、法律による厳格な拘束を受けた行為のことです。一言で言えば、法律によって具体的に指示されたこと以外は一切行えない行為のことで、その例として、建築確認が挙げられます。
建築確認は、建築されようとする建物が、適法がどうかの確認するだけの行為です。まさに、覊束行為の典型です。
また、損失補償は、補償の額を行政庁の判断で増減することはできませんので、これも覊束行為ということができます。
これに対して裁量行為とは、法律が行政機関に広範な授権をしているので、行政機関の政策的・行政的判断によって行われる行為ということができます。
この裁量行為には、
①要件裁量
②効果裁量――という分類があります。
①の要件裁量とは、要件が充足されているかどうかの認定における裁量のことです。
一方、②の効果裁量とは、行政行為そのものを行うかどうか、行うとしたらどのような行為を行うかの認定における裁量のことです。
例えば、「医師が医師としての品位を失うような行為を行った時には、厚生労働大臣が免許を取消したり、期間を定めて医業の停止を命ずることができる」という規則があった場合、品位を失うような行為とはどのような行為かを行政庁の判断に任せるなら、要件裁量に当たります。
一方、免許の取消しか、営業停止か、またはいずれの処分もしないかを行政庁の判断に任せるなら効果裁量の一つといえるのです。
ただし、行政が複雑化した現在では、要件裁量か効果裁量かをきっちりと決めるのは難しくなってきており、少なくとも、事例問題の処理ということに関しては、それほど重要な概念ではないと言えそうです。
さて、話は、覊束裁量と自由裁量の分類に移ります。
覊束裁量行為は前述の覊束行為とは異なり、一応裁量の存在が予定されているものを指しますが、それは文言上のことであって覊束という言葉からも分かるように実は法が行政を拘束しているのです。
具体的には、法律が客観的な基準(明文には表れていなくても、通常、人が社会通念で、その基準を満たすかどうかを判断することができる基準)を定めていて、その基準に従うことを求めているものが覊束裁量と呼ばれるものです。
一般人でも判断ができるような法基準に従って行政行為を行わなければならない、となると行政が独断で判断して行為をするわけではないので、裁量行為とはいえ、その裁量の余地は、通念上の基準に合致するかどうかの判断しか認められないことになります。
さらに、この基準は法が定めているので、この基準に反した場合、つまり裁量を誤った場合は、その行政行為は違法と評価されます。覊束裁量は、客観的な基準によるので、裁判所の判断と同様と考えられるため、法規裁量と呼ばれることもあります。
覊束裁量の例には、運転免許の取消し、皇居外苑の使用許可、農地賃貸借の設定・移転の許可――などがあります。ただし、これらはすべて行政学上の許可に含まれるものということに注意してください。というのは、許可は、本来国民の自由に任せるべきところを、特別に制限したものを解除することです。ですから、言い換えると、自由を制限できるのがどんな場合かは、客観的な基準によって決められるべきだ――と言えるのです。
一方、自由裁量は、どのような行政行為をいつするかという点について、純粋に行政庁の政策的・専門的判断に委ねられた裁量のことです。法による拘束がないことから、法規裁量に対して便宜裁量とも呼ばれます。
この場合、行政府は何が行政の目的に合致し、公益に適するかを、専門的な立場から自由に判断することになります。一般人にとって判断可能な基準に従う必要はありません。
ということは、少々裁量を誤っても、誤ったことの判断は法に照らしては行えないことになります。このように、裁量を誤ったにすぎない行政行為を違法行為に対して、不当行為といいます。
当・不当の判断は、法に照らして判断することができないので、原則として不当行為に司法審査は及ばないと言えます。
覊束裁量と自由裁量を区別する理由は、かつては司法審査が及ぶか及ばないかを分ける基準とされてきましたが、今日では、覊束裁量は裁量の逸脱や濫用が認定しやすく、自由裁量では逸脱や濫用の認定が難しいと言う差くらいしかありません。